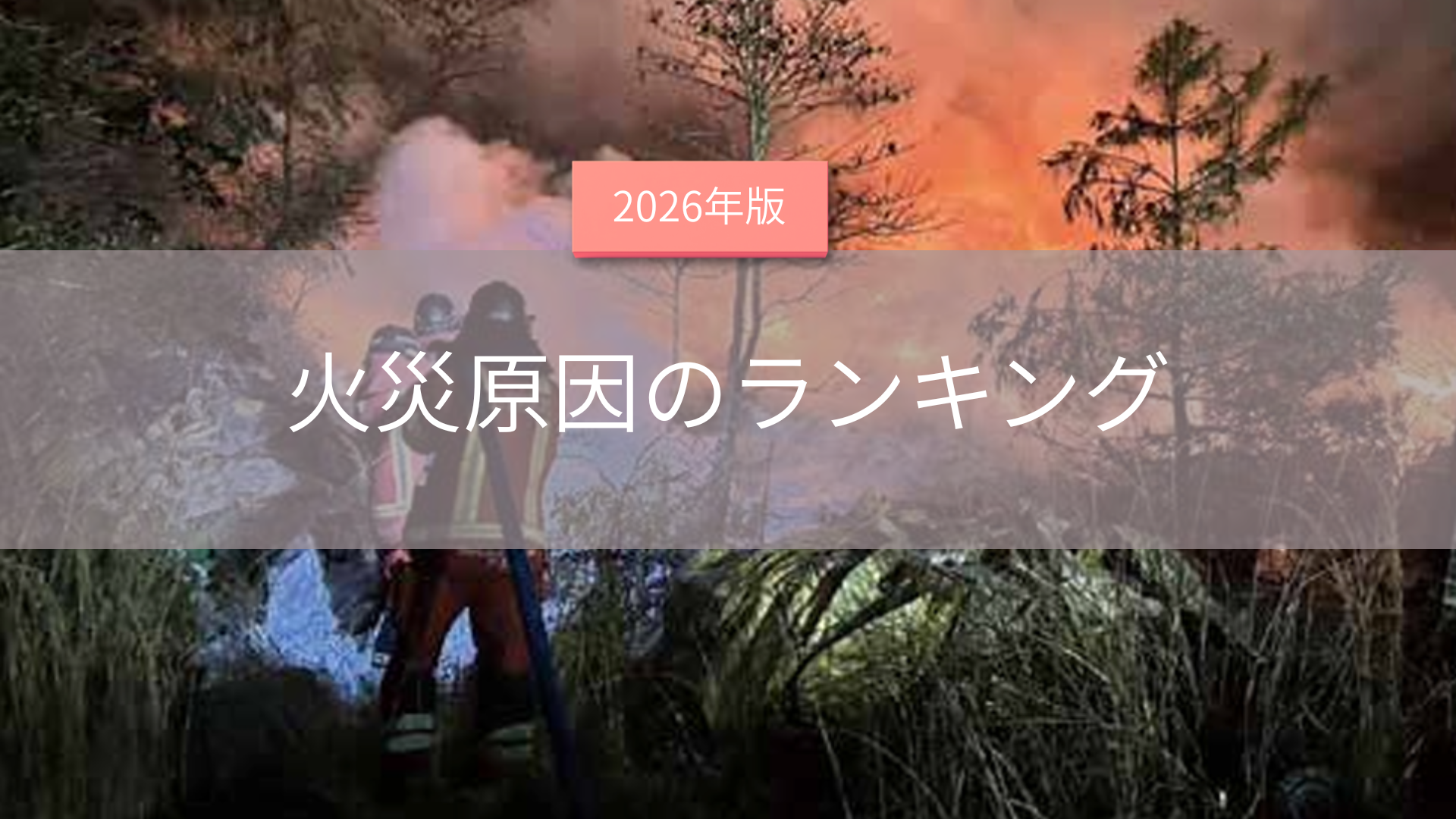大地震が発生すると、火災による被害も心配されます。近年でも、阪神淡路大震災や東日本大震災では火災が複数箇所で発生し、地域一帯が焼失する惨事になったのは、記憶に新しいところです。
そもそも、地震によってなぜ火災が発生するのでしょうか。また、地震による火災を防ぐためには何に注意すればよいのでしょうか。日頃からできる対策も含めて、地震火災を防ぐ方法を紹介します。
目次
1.地震による火災はなぜ起きるのか
地震時に火災が発生する原因の一つに、「暖房器具」があります。例えば、地震で落下したカーテンや転倒した家具の近くにストーブなどの暖房器具があると、引火して燃え広がることが考えられます。
また、「ガス管や電気配線が破損」も出火原因の一つです。家屋が倒壊してガス管や電気配線が破損すると、ガス漏れやコードから飛び散った火花によって火災を引き起こすケースもあります。
「通電火災」も、注意が必要です。通電火災とは、地震による停電が復旧した際に、転倒した電化製品が通電状態となり火災を引き起こす現象です。具体的には、地震で布団の上に転倒した電気ストーブをそのまま放置し、通電されたときにストーブの熱で布団に引火。それが燃え広がり火災が発生するというケースがあります。これは、阪神淡路大震災でも複数確認された火災原因です。ほかにも、白熱灯など照明器具が転倒し、可燃物に接触した状態で再通電して着火するケースもあります。
津波による「津波火災」も、大きな火災につながる一因です。津波は、家屋のほか自動車や漁船、プロパンガスなど、さまざまな可燃物を押し流します。これらが火種となって燃え広がり、大規模延焼をもたらすのです。
もっとも、津波火災は防ぎようのない点もありますが、先に挙げた「暖房器具による火災」や「通電火災」などは、日ごろから注意していれば防げるものでもあるのです。
2.もし地震が起きてしまったら
大きな地震が発生した際、火災を防ぐために取るべき行動として、以下の点が挙げられます。
地震直後に取るべき行動
地震の揺れが収まったら、まずガス機器の火を消します。現在は、大地震が発生するとガスメーターが自動的にガスを遮断するため、揺れが収まってから火の始末を行いましょう。
停電になったら、電化製品のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。石油ストーブやファンヒーターを使っている場合は、油漏れの有無も確認します。
避難する際には、ブレーカーを落としてから家を出ます。最近は「感震ブレーカー」という、大きな揺れを感知したら自動的にブレーカーを落とすグッズも登場していますので、あらかじめ設置しておくと安心です。
地震後しばらく経った後に取るべき行動
ガス機器や電気機器の使用を再開するときは、「機器が破損していないか」「近くに可燃物がないか」を確認します。また、電化製品は通電後に、煙やにおいなど異常がないかも注意しましょう。
3.地震発生時に火災が起きないよう日頃からできる対策
地震による火災を防ぐには、日ごろから対策を講じることも大切です。具体的な対策について紹介します。
家具の固定
倒れやすい家具を固定するのは、身を守るだけでなく、火災予防にも効果的です。L型金具で壁にネジ止めしたり、突っ張り棒を使ったりして転倒防止策を講じましょう。
可燃物は暖房器具の近くに置かない
カーテンや衣類、紙類などの可燃物が暖房器具の近くあると、地震時に引火するおそれがあります。暖房機器の近くに可燃物を置かないよう、日ごろから整理整頓を心がけることが大切です。
最近では、転倒すると自動で電源が切れる暖房器具が一般的です。こうした安全装置付きの機器を選ぶのも一手でしょう。
住宅用消火器を設置する
万一火災が発生したときに備えて、住宅用消火器を設置することも大切です。単に設置するだけでなく、消火器を正しく使えることも重要なポイント。勤務先や地域の防災訓練などで消火器を使う機会があれば、正しい使い方を習得しましょう。
消火器の使い方に不安がある方は、市販の簡易消火具を手元に置いておくと安心です。
4.地震火災はどこで発生するかわからない
日本では大きな地震が発生するたびに、火災による被害を受けてきました。
歴史上もっとも大きな地震火災が、1923年の関東大震災です。この地震では10万人以上が亡くなったといわれますが、そのうち7割が火災による死者でした。ただ、当時は「かまど」で食事をつくる家庭が多いなど、現在とは生活スタイルが異なるため出火原因も異なります。
近年起きる地震火災は、通電火災をはじめ電気関係が多くを占めるようです。例えば、1995年の阪神淡路大震災では293件の火災が発生していますが、そのうち原因が判明した火災の約6割が「通電火災」といわれます。
また、2016年の熊本地震では、通電後に熱帯魚のヒーターから発火して火災が発生するなど、16件の火災が報告されています。さらに2018年の大阪府北部地震では、転倒した家具により電気ストーブのスイッチが入り、火災が発生するという事象がありました。
このように、近年の大地震では電気火災が多くを占めており、暖房器具やコンロだけが出火原因とはいえないのです。身の回りで火災の発生するリスクが高い箇所を、あらかじめ把握しておくことも重要なポイントといえます。
5.まとめ
国は、首都直下地震が発生した際の被害について、最悪のケースで死者が約2万3,000人、このうち7割にあたる約1万6,000人が火災で命を落とすと想定しています。出火件数は、約2,000件。同時多発で発生するため、現在の消防力では限界だという指摘もあります。
大きな地震はいつ、どこで発生するかわかりません。ただ、大地震による火災は対策を講じることで防ぐことも可能です。いざというときのために、できることから始めてみてはいかがでしょうか。