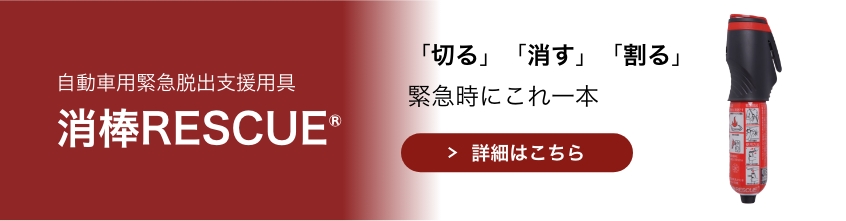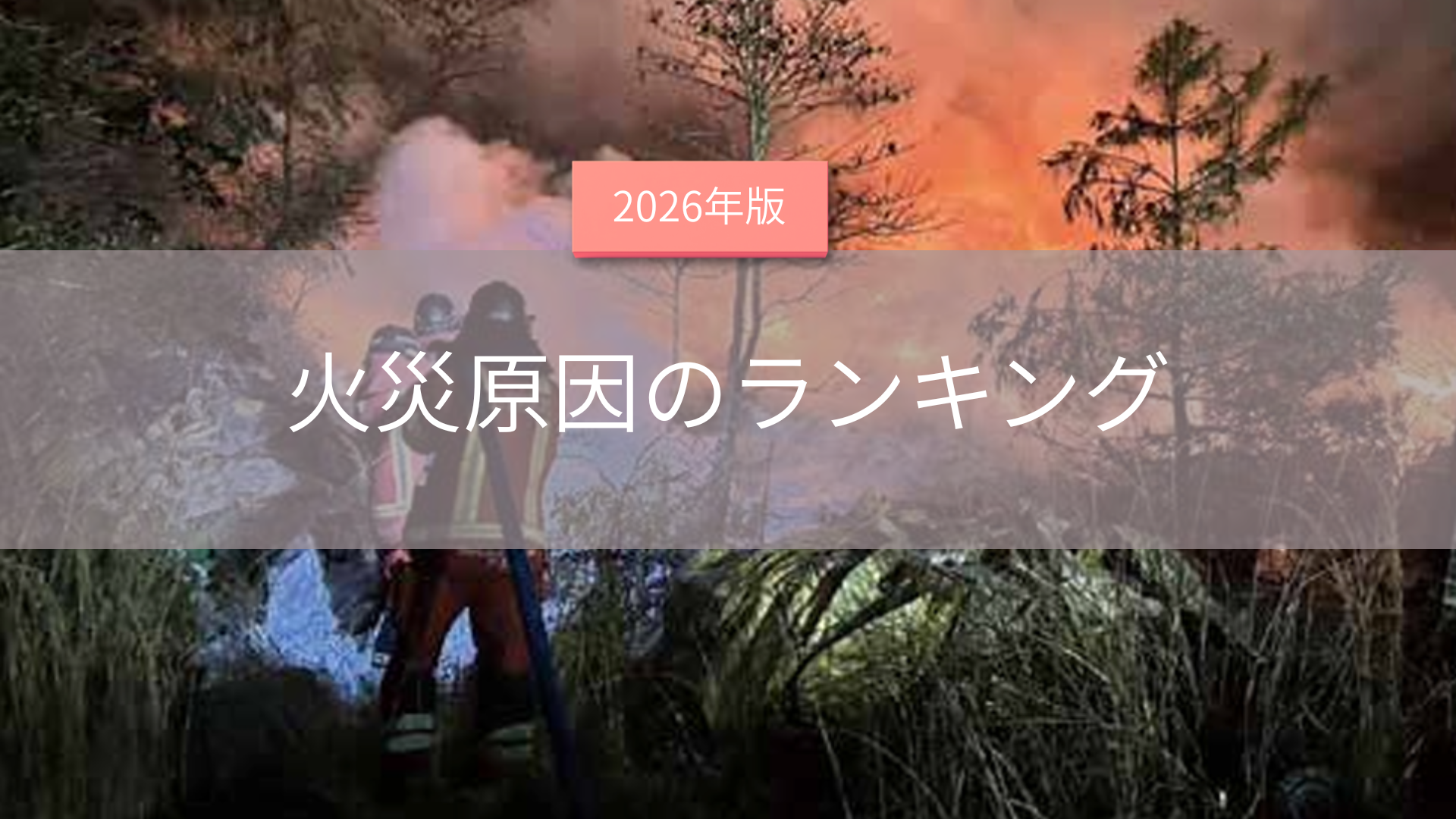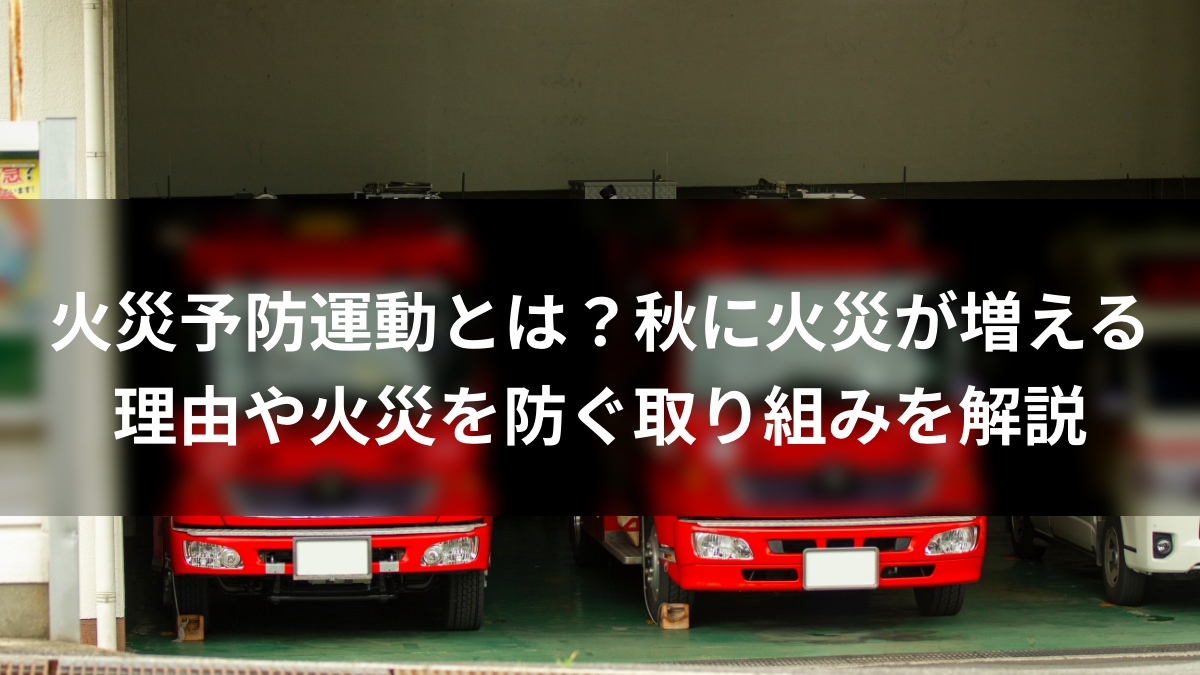
総務省消防庁は、国民一人ひとりの防火意識を高め火災を防ぐことを目的に、「全国火災予防運動」を年2回(春季と秋季)実施しています。 この運動の期間中には、消防庁や自治体などを中心に、さまざまなイベントが展開されます。ただ、個人や企業も、この運動を機に消火設備を点検するなど、火災予防に努めたいところです。
今回は、全国火災予防運動に関する基礎知識を中心に、防火意識を高める取り組みやポイントについて解説します。
目次
1.全国火災予防運動とは?
全国火災予防運動とは、消防庁が制定する「全国火災予防運動実施要領」に基づいて実施される啓蒙活動のことです。
この実施要領には、全国火災予防運動の目的が記載されています。その目的とは、「火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐ」とされています。
1年を通して火災の出火件数が多いのは、12月~3月ごろです。この時期は、空気が乾燥することや強風が吹きやすいことなど、火災の発生・延焼に注意が必要とされています。そこで、火災が多くなる時期を前に11月9日から11月15日までを「秋季全国火災予防運動」、また、1年で最も火災が多いとされる春を前に3月1日から3月7日までを「春季全国火災予防運動」として、防火意識を向上させる取り組みが展開されています。
火災予防運動の由来と時期
全国火災予防運動の歴史は古く、今から100年近く前の1930年に始まったといわれます。ただ、時期に関しては何度か変更されており、現在の春季(3月1日から3月7日)と秋季(11月9日から11月15日)が決まったのは、1989年です。
春季に関しては、消防組織法が施行された3月7日が「消防記念日」に制定されたことから、この日を含む前の1週間が全国火災予防運動として1950年に決まっています。一方で秋季に関しては、11月9日が119番の語呂合わせで「消防の日」と定められたことから、この日を含む後の1週間が全国火災予防運動の時期になりました。
2.火災が増え初める秋口 - 出火原因で多いものは?
秋になると空気が乾燥し、暖房器具を使う機会が増えるなど、火災が発生する条件が生まれやすくなります。実際に、消防庁がまとめた「全火災の月別出火件数」によると、例年12月ごろから増えはじめ3月にピークを迎える年が多いようです。
出火原因別でみると、最も多いのは「たばこ(3,209件)」、次いで「たき火(3,105件)」「こんろ(2,771件)」と続きます。ちなみに住宅火災だけに限ると、1位は「こんろ(1,818件)」、2位は「たばこ(1,303件)」、3位は「ストーブ(864件)」です。 これらの出火原因について、深掘りしてみましょう。
(※)出典:消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf
たばこ(全火災で1位・住宅火災で2位)
全火災の出火原因で最も多いのが、「たばこの不始末」です。寝たばこをして布団に引火したり、不適当な場所に捨てて山火事などに発展したりするケースが多くみられます。
たき火(全火災で2位・住宅火災で11位)
強風などで炎が急激に大きくなったり、火の粉が舞い上がって住宅などに飛び火したりすることで、火災が発生することがあります。また、残り火が十分に消火されず数時間後に再燃して、山火事などにつながるケースも報告されています。
こんろ(全火災で3位・住宅火災で1位)
住宅火災で1位の「こんろ火災」。揚げ物をしているときにその場を離れてしまい、食用油に引火して火災につながるといったケースも少なくありません。また、油かすや着衣などに引火し、火災を引き起こすこともあります。
ストーブ(全火災で10位・住宅火災で3位)
ストーブの周りに燃えやすいものを置いたことが原因で、火災になるケースが多いようです。例えば、洗濯物を乾かすために近くに置いたり、寝ている間に布団がストーブに触れたりして火災になる事例が報告されています。
3.火災予防の意識を高めるために必要なこと
火災は家などの財産だけでなく、命を奪うこともあります。2022年に火災で亡くなった人は1,195人(自殺を除く)。このうち7割以上が、65歳以上の高齢者が占めるというデータもあります。
火災による悲劇を生まないためには、何より「火災を起こさないこと」が大事です。消防庁では、火災の予防や命を守るために「住宅防火 いのちを守る10のポイント」を公表しています。このなかには、日ごろから取り組むべき「4つの習慣」と「6つの対策」が紹介されています。具体的には、以下の通りです。
4つの習慣
- 寝たばこは絶対にしない、させない
- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
- こんろを使うときは火のそばを離れない
- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策
- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する
- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
火事を発見したら「初期消火」も大事
どれだけ予防に努めても、火災を防げないこともあるでしょう。もし火事を発見したら、消防に通報するのはもちろん、自らも消火器などで初期消火を試みることも大事です。火が燃え広がらないうちに消火活動を行えば、被害を最小限に食い止められます。 ただし、火事を発見したときに火の勢いが強かったり煙が広がっていたりするときは、逃げ遅れる可能性があります。自力での対処が困難だと判断したら、消火活動よりも避難を優先させることが大切です。
4.まとめ
初期消火を迅速に行うには、消火器の使い方を把握しておくことも大事です。とはいえ、日常的に使うものではありませんから、使い方に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。そのような方には、手軽で使いやすい「簡易消火具」もおすすめです。 当社が開発した二酸化炭素消火具「消棒Rescue(R)」は、一般的な消火器よりも軽量・コンパクトで、いざというときに迅速な初期消火を実施できます。消防法にも準拠したエアゾール式簡易消火具で、初期消火に有効です。消棒Rescue(R)は自動車内の設置を念頭にシートベルト切断機能及びドアガラス(強化ガラス)破砕機能(脱出ハンマー)が備わっていますが、卓上ホルダーを使えば、家庭、オフィス、工場等の初期消火用具としても設置可能です。
「消棒Rescue®」は、最近増えているパソコン、スマートホン、モバイルバッテリーなどリチウム電池臓製品からの発熱、出火にも、対象物を汚さない噴射が可能です。