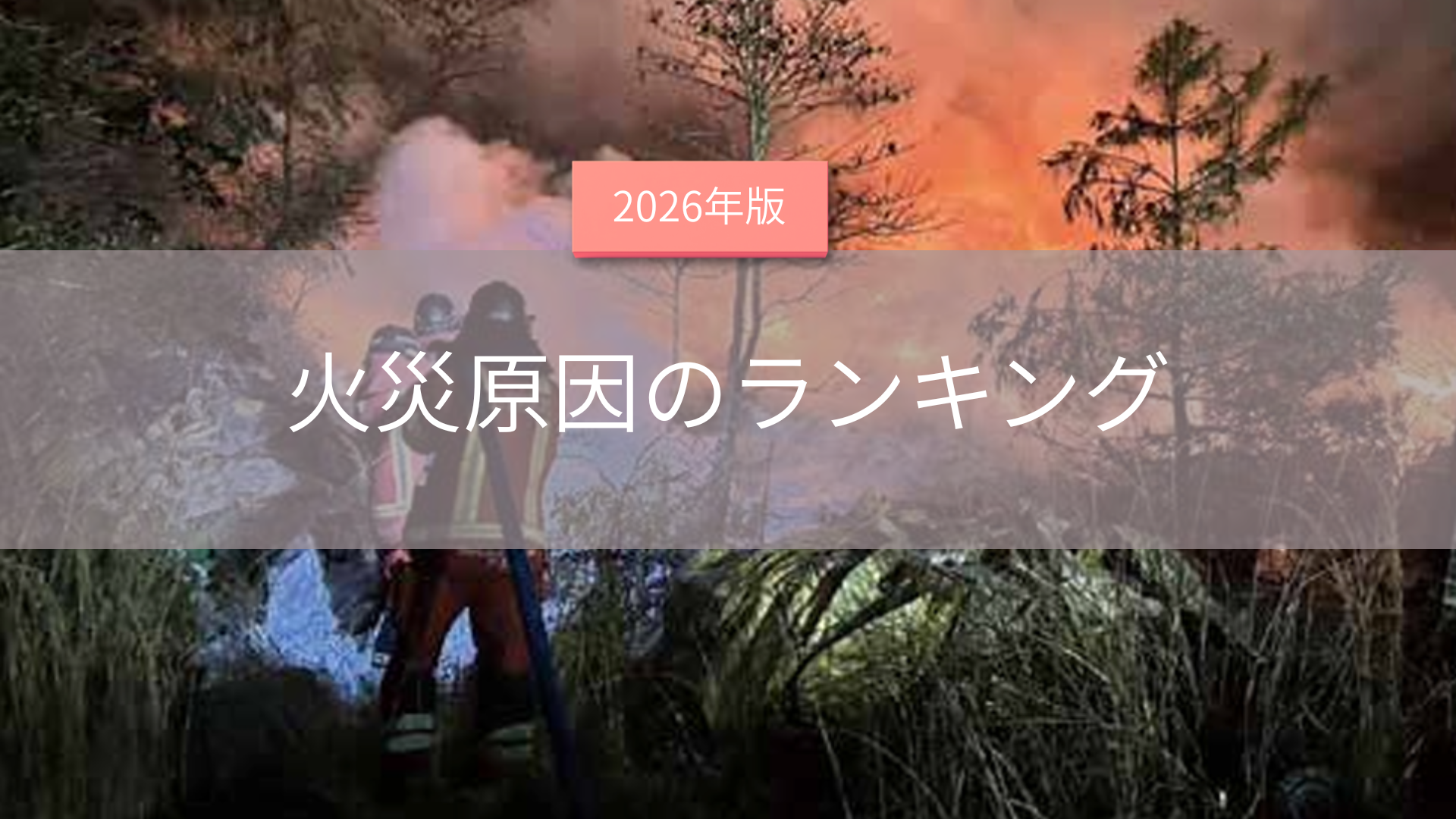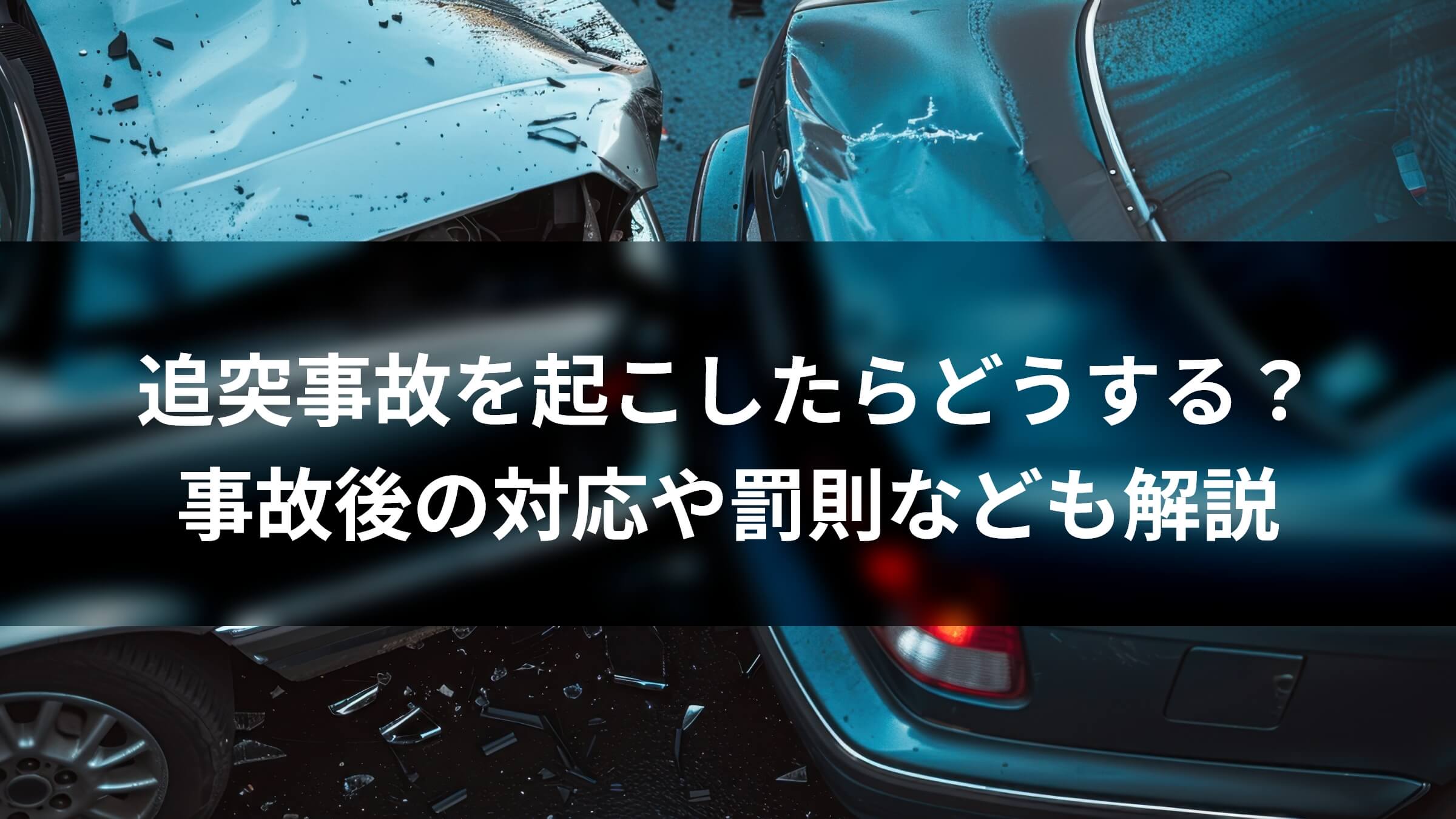
自動車同士の事故で、発生件数がもっとも多いとされるのが「追突事故」です。追突事故は、正面衝突など他の事故と比べて死亡率は低いといわれます。ただ、高速道路での玉突き追突事故など、状況によっては命にかかわるケースもありますので、事故後の対応を含めて必要な備えをすることが大切です。
ここでは、追突事故の原因や過失割合、万が一事故を起こした場合の対処法などを中心に、いざというときに備えておきたいポイントをお伝えします。
目次
1.追突事故とは
追突事故とは、同じ方向に走る前方の車に、後方の車が衝突する交通事故のことです。前方の車が徐行や停車をしている場合でも、後方から衝突したら追突事故になります。また、高速道路などで起きる玉突き事故も、追突事故の一種です。
ちなみに、逆方向から来る車に衝突する場合は「正面衝突事故」、前の車を追い越す際に後方の車が接触したときは「接触事故」といいます。
追突事故の発生件数
追突事故は、車同士の交通事故のなかで最も多い事故といわれます。内閣府の「交通安全白書」によると、2022年に発生した交通事故の件数は、30万839件です。このうち追突事故は9万1,835件で、全体の30.5%を占めます(※)。
なお、近年は交通事故の発生件数が減少傾向にあり、追突事故も減っています。最近では、前方の車に接近すると自動ブレーキが作動するAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を備えた車が増えたことも、追突事故が減少している一因として考えられます。
とはいえ、全国では1日平均250件もの追突事故が発生しており、決して他人事とはいえないでしょう。
(※)参考:内閣府「令和5年交通安全白書」
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r05kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html
高速道路の事故は増えている
一方で高速道路では、追突事故をはじめ交通事故の件数が増えているようです。首都高速道路によると、2023年度の事故発生件数は9,017件で、前年度と比べて624件(7.4%)増えたと報告しています。このうち追突事故は3,905件で、全体の43.3%を占めます(※)。
高速道路は一般道よりスピードが出ているため、十分に車間距離を取らないと追突事故につながりますし、命にかかわる事故につながるケースも少なくありません。事故を防ぐためにも、安全運転に心がけることが大切です。
(※)参考:首都高速道路「事故・車両故障・落下物の現状について」
https://www.shutoko.co.jp/company/database/accident/
2.追突事故が起きる理由
自動車同士の追突事故は、なぜ発生するのでしょうか。追突事故が起きる理由をお伝えします。
わき見運転(ながら運転)
外の景色などに気をとられ、気づいた時には前方の車に衝突していたというケース。いわゆる「ながら運転」が原因の一つです。
最近は、カーナビやスマートフォンの操作による追突事故が増えています。特に運転中のスマホ操作は大変危険です。罰則も強化されていますので、スマートフォンを操作する際には安全な場所に停車してから行いましょう。
動静不注視(だろう運転)
動静不注視とは、楽観的な予測による運転行為で事故を起こしてしまうことです。例えば、信号が青に変わった瞬間に「前の車が動くだろう」と思い込み、前の車が発進する前にアクセルを踏み込んで追突事故を起こすというケースも、動静不注視の一例です。
漫然運転
漫然運転とは、運転に必要な注意力が欠けた状態で運転することです。具体的には、運転中に考え事などをして信号を見落としたり、適切な車間距離を保てなかったりし、追突事故を起こしてしまうケースがあります。
その他
ほかにも、ブレーキとアクセルの踏み間違いで追突事故を起こす「操作ミス」もあれば、居眠り運転や飲酒運転、スピードの出しすぎといった交通違反による事故もあります。また、最近問題になっている「あおり運転」も追突事故になることがあります。
3.追突事故を起こしたときの罰則
交通事故を起こした場合、状況によっては違反点数や反則金・罰金が生じます。では、追突事故の場合は、どのような罰則が想定されるのかを考えてみます。
追突事故の違反点数と反則金・罰金
交通事故を、違反点数や反則金・罰金の側面でみたとき、「物損事故」と「人身事故」で大きく異なります。
物だけに損害を与える物損事故の場合、原則として違反点数はありません。ただし、住居などの建造物に追突すると違反点数が加算されます。点数は事故の状況によって異なり、一概にはいえません。また、何を破損したかに限らず、加害者には修理費などを支払う責任が生じます。
一方で、人を死傷させる人身事故の場合は、違反点数が加算されます。こちらも事故や相手の状況によって点数が異なりますし、反則金もしくは罰金も違います。ちなみに「反則金」とは、違反点数が6点未満の軽微な交通違反で科される行政処分で、金額は3,000円~40,000円と決まっています。これに対して「罰金」とは、違反点数が6点以上のときに科される刑事処分です。金額は裁判で決まります。
追突事故の過失割合について
追突事故の過失割合は、基本的には「追突した車が10」「追突された車は0」です。これは、後ろを走る車には十分な車間距離を保ち追突を避けるよう運転することが、法律で定められているからです。
ただし、追突された車にも過失が認められるケースがあります。例えば、高速道路で前の車が急ブレーキをかけ追突した場合、過失割合は「5:5」などになることがあります。これは、高速道路では停車してはならないという決まりがあり、前の車にも過失が認められるからです。
ほかにも、前の車が追越しを妨害したり不要な急ブレーキをかけたりといった「あおり運転」が認められるケースや、駐停車禁止の場所で駐車中の車に追突するといった交通違反が認められる場合も、追突された車に過失が生じることがあります。また、玉突き事故では、基本的には最初に追突した車に過失が生じますが、事故の原因・状況によっては真ん中や一番前の車にも過失が生じることがあります。
こうしたケースの過失割合は、裁判で決まるのが通例です。
4.追突事故を起こしたときの対処方法
追突事故を起こしたとき、あるいは起こされたときは、慌てず冷静に対処することが求められます。そのためには、あらかじめ対処の流れを把握しておくことも大切です。
ここで、追突事故の具体的な対処の流れについて確認しておきます。
安全確保・救助
車を動かせるときは、路肩など安全な場所に車を移動させます。車を動かせないときは、発炎筒や三角表示板を設置して後続車に知らせます。また、けが人がいるときは救助を優先しましょう。
警察に連絡
安全を確保したら、警察に連絡します。軽微な事故でも通報が義務付けられています。必ず連絡しましょう。
事故状況の記録
車の破損箇所など事故の状況は、個人でも記録しておきます。できれば写真を撮っておくと、保険を申請する際などに役立ちます。また、事故の相手の名前や住所、連絡先、車のナンバーなども確認しておきましょう。示談交渉などをする際に役立ちます。
示談交渉
加害者が示談交渉をするときは、加入している保険会社に相談します。なお、過失が0の被害者は保険会社に交渉してもらえないため、自分で交渉するか弁護士に交渉してもらいます。
5.万が一の追突事故のために備えておきたい安全グッズ
追突事故の状況によっては、車内に閉じ込められて脱出できないケースも考えられます。燃料やオイル漏れから車両火災につながることもあるでしょう。こうした非常事態に備えて、自動車用の「緊急脱出ツール」や「簡易消火具」などを車内に備えておくのも一手です。
ワイピーシステムが提供する緊急脱出ツール「消棒Rescue®」には、車内から脱出するために必要な「ガラス粉砕ハンマー」「シートベルトカッター」が備わっています。
ガラス粉砕ハンマーは、力の弱い人でも確実に割れるように設計。ドアの窓などを短時間で粉砕できます。
また、事故による衝撃などでシートベルトが外れないことを考慮し、シートベルトカッターも搭載。1本あたり2秒未満で切れ、迅速な脱出をサポートします。
さらに、車両火災が発生した際に初期消火ができる「小型二酸化炭素消火具」も、消棒Rescue(R)には備わっています。この消火具は消防法に準拠しており、ガソリン車やハイブリット車、電気自動車などのバッテリー火災にも有効です。
自動車の安全性能が高まっても緊急脱出ツールは必須アイテム
技術の進歩にともない、自動車の安全性能は日々進化しています。最近では、車内に閉じ込められても自動で窓が開く機能を備えた車も登場。水没事故などに遭遇した際でも、容易な脱出をサポートしてくれます。
ただし、これらの機能は100%安全を保証しているものではありません。事故の状況によっては機能が作動せず、車から脱出できないケースもあるのです。こうした場合でも緊急脱出ツールがあれば、命を守れる確率が高まりますから、より安心です。
ワイピーシステムの「消棒Rescue®」は、1つで「割る」「切る」「消す」の3役をこなす緊急脱出ツールです。国家規格(JIS)D5716認証品で、大手自動車メーカーでも採用実績があります。国のお墨付きをいただいたアイテムですから、ぜひ車内に1台備えてはいかがでしょうか。
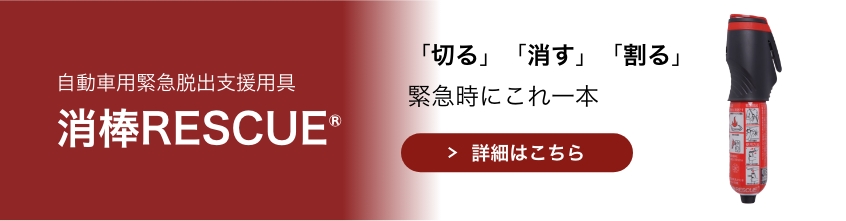
6.まとめ
追突事故を防ぐ基本は、安全運転を心がけることです。「わき見運転をしない」「車間距離を詰めすぎない」などの交通ルールを順守するのはもちろん、ブレーキを踏むタイミングやライトを点灯するタイミングなども考慮し、運転に集中しましょう。
とはいえ、どれだけ安全運転に心がけても事故の発生を0にすることはできません。事故を起こしたら、迅速かつ必要な対処ができるよう、緊急脱出ツールを含めて備えることも大事です。